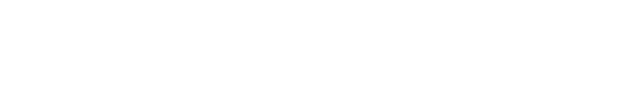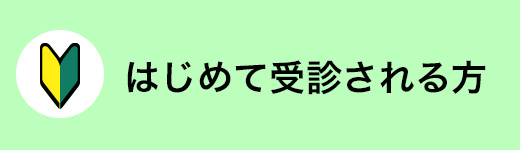【院長ブログ】自然免疫と皮膚疾患に関する講演を行いました(2025年7月29日)
こんにちは。五条桃谷皮膚科クリニックの院長、前田です。
先日、大塚製薬株式会社にて「自然免疫と皮膚疾患」に関する社内講演を行わせていただきました。
今回の講演では、異種移植における拒絶反応を出発点として、自然免疫の仕組みや皮膚疾患との関わりについて解説いたしました。
まず、異種移植における超急性拒絶反応の原因となる、α-Galに対する自然抗体についてご紹介し、さらにNK細胞・マクロファージ・好中球といった自然免疫細胞による細胞性拒絶反応についても詳しく説明しました。
NK細胞と免疫調整
NK細胞(ナチュラルキラー細胞)は、活性化レセプターと抑制性レセプターを発現しており、それぞれ異なるメカニズムで免疫反応を制御しています。
-
活性化レセプターは細胞質内の末端が短く、単体ではシグナルを伝えにくい構造ですが、DAP10やDAP12といったアダプター分子と結合することで、活性化シグナルを伝達します。
-
抑制性レセプターは、ITIM(免疫受容体チロシンベース抑制モチーフ)を介して抑制的なシグナルを誘導し、免疫応答の暴走を防ぎます。
これらのレセプターのバランスによって、NK細胞は適切な免疫応答を担っています。
マクロファージ・好中球と糖鎖認識
また、マクロファージや好中球は、表面に発現するレクチンを通じて異物表面の糖鎖を認識し、活性化されます。
レクチンと糖鎖の結合は緩やかであるものの、ここからも活性化シグナルや抑制シグナルが誘導され、免疫反応の制御に重要な役割を果たしています。
おわりに
今回の講演では、こうした自然免疫の基本的な仕組みと、それが皮膚疾患の病態や治療にどのように関係してくるかについて解説しました。
自然抗体や自然免疫細胞が、今後さらにアトピー性皮膚炎や乾癬といった疾患への理解や治療法の開発に寄与していくことが期待されます。
また、モイゼルト軟膏(デルゴシチニブ)のような外用薬にも、まだ解明されていない作用メカニズムが存在している可能性があり、今後の研究の進展により、より幅広い皮膚疾患への応用が進むことを願っております。
このたびの講演の機会をいただいた大塚製薬株式会社の皆様に、あらためて御礼申し上げます。